「味の素」とは、グルタミン酸ナトリウム粉末の商品名である。

日本で古来より活用されてきた第5の味覚「うま味」をつかさどる重要な物質だ。
砂糖は甘味、塩は塩味を単体でつかさどるように、「味の素」はうま味を単体でつかさどっている。
これと食塩を混合した調味料は「アジシオ」として市販されている。
①驚
2か月ほど前、私は「味の素」に魅入られ、とにかく3食すべての食事に可能な限り多量の「味の素」を投入して過ごしていた。
そもそも、この「味の素」なる調味料、単なるうま味単体のくせして「味」の素を名乗るとは僭称も甚だしいと思われた。
しかし、実際に「味の素」を食事にかけると、まるでそこからアニマのごとく”味”が湧き出してくるような感覚に襲われる。
料理に対して均質に”美味しい”という属性が付与されるのだ。
端的に言って、「味の素」をかけると料理が”美味くなる”。
そして、さらに不可解なことに、「味の素」には「適量」という概念がないように思えた。
かければかけるだけ、量に比例して”美味しく”なるのである。
私はこの現象を体験し、強い驚嘆を覚えた。
この事実が本当なら、「味の素」は料理という文化そのものを破壊する存在である。
なぜなら、料理に対して砂糖をかければかけるだけ甘く、塩をかければかけるだけ塩辛くなるのと同様に、「味の素」をかければかけるだけ”美味しく”なるならば、もはや手の込んだ手順で厳選された肉や野菜を煮込む必要も、適切な産地で採れた種々の調味料やハーブを配合する必要も、代々秘伝のタレを日夜仕込み続ける必要もないからである。
事実、私は試した。
単にスライスして焼いただけの芋に、少しばかりの塩と大量の「味の素」をかけて食ってみたのだ。
それは非常に”美味く”、不満足なところのない完成された味わいだった。
またある日は、ラーメンの中に大匙6杯ほど入れてみた。
口中にぺっとりと貼りつくような濃厚なうま味で、食事後もしばらく口中が”美味しさ”に包まれていた。
また、ある日タイの刺身を食っていたところ、何か物足りなかったので、パラリと「味の素」をかけてみた。
すると刺身は爆発的に”美味く”なり、それは「味の素」をどれだけかけても過剰になることはなかった。
日本には、うま味の少ない白身魚を昆布締めにしたり血抜き熟成させたりする文化がある。
もはやそんな手間をかける必要があるのか、この「味の素」締め刺身の手軽さと”美味さ”の前では疑問を禁じえなくなる。
そもそも、砂糖や塩はかけすぎればいずれ「甘/塩辛すぎる」という状態に陥る。
ところが、うま味に関しては「うま過ぎる」という状態は存在しない(したとしても、それは口語的な誉め言葉であろう)。
人間が生肉を貪り食っていた状態から「料理」なる奇怪な文化を紡ぎ始めた果てにあるものが「”美味い”食事」であるならば、「味の素」はまさにその最果てであり、それより先に「料理」が紡ぎうる未来は存在しない。
それにもかかわらず、「味の素」は軽く見られていすぎやしないだろうか。
今のところ世界から料理という文化は失われていないばかりか、どこの料理本や料理番組を見ても、レシピに
「味の素・・・可能な限り多量」
とは書かれていない。
そればかりか、
「『味の素』は使わない方が正統である」
という考えすら根強い。
食品添加物に対する心理的忌避反応からくる部分もあるのだろうが、それにしてもここまで手軽に”美味しさ”という属性を付与してくれるアイテムであるにしては、「味の素」は軽んじられすぎているように思えてならない。
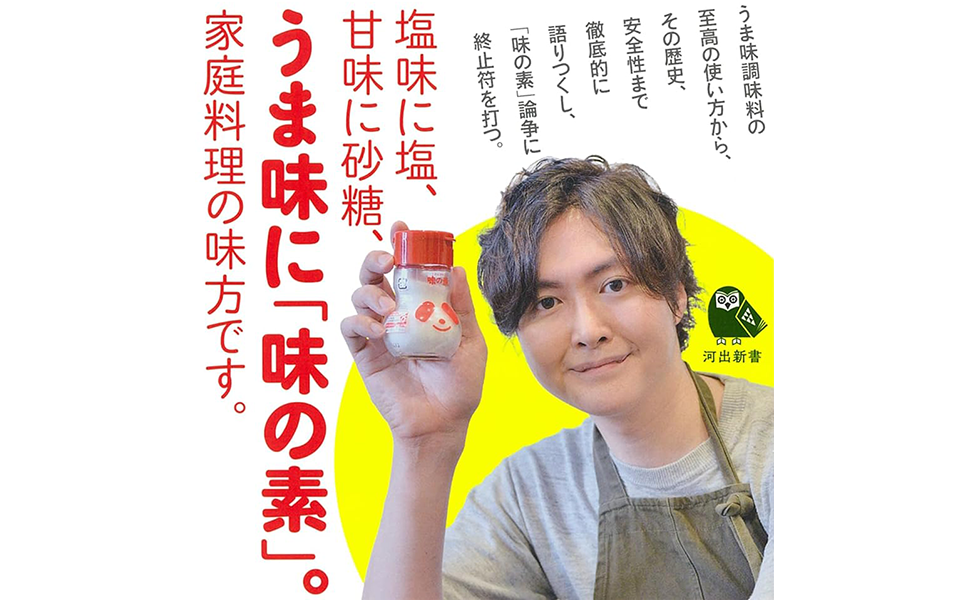
②解
しかし、私が「味の素」の探求を始めてからしばらく経ったある日、私はあることに気づく。
ある日、白湯に塩と「味の素」を溶いて「お吸い物のイデア」を作ってみたときのことだった。
湯気立つその透明な液体は、当然ながら全くの無臭である。
お吸い物が無臭であるという違和感は強く、その時点で私はその液体を料理としては「不味い」と評価した。
しかし、その液体は同時に”美味く”もあった。
これは矛盾ではない。
「味の素」が任意の物体に対して”美味しい”という属性を付与するアイテムである以上、「味の素」がかかった食事は無条件に”美味い”。
しかし、「味の素」の美味さを判定している主体は恐らく、心身二元論で言うところの”身”であって、”心”ではない。
すなわち、この瞬間に人の感覚は精神(理性)と身体(野生)とに引き裂かれ、その両方を宿すこの己は、否応なしにその食い違う合議を目の当たりにすることになるのである。
これは、些か野卑な例えで申し訳ないが、眼前に裸体の醜女が現れた状況と似ている。
野性的反射によってつい下腹部が熱くなることはあるかも知れないが、それは理性的恋慕の情とは全く分けて考えるべきものであろう。
これと全く同様の機序で、「味の素」は人間の野生に”美味しさ”を働きかける。
事実、私がハイボールに「味の素」をかけて飲んでみたところ、それはまさしく酷い味だったが、にもかかわらず”美味い”という属性が付与されていることははっきりと理解できる味だった。
身体は喜ぶ、しかし心は吐き気を催すような味とでも言おうか。
ここで俄に明らかになる事実がある。
食事の美味さにおいて、野性的・身体的美味さと理性的・精神的美味さという2軸が存在することである。
前者は単なる栄養素、人間という動物の生存に普遍的に直結する美味さで、仮にミキサーで食事をバラバラにしても変化しない美味さであろう。
後者は恐らく料理の技巧が関係する美味さで、動物としての普遍的な生存に直結するというより、もっと個別の人間個体に特異的な趣味嗜好や、後天的な文化の影響を受けるものだろう。
厄介なことに、これら2つの美味さは、恐らく互いに融合し合っていて、峻別不可能な領域が大きそうに思える。
生牡蠣の美味さを単に栄養素だけで説明するのは本質的ではないし、サルミアッキの美味さを文化だけで説明するのもまた道理に合わないだろう。
そして、どうやら人間がまだ「料理」という文化を手放す必要がないらしいことも、この段になってはっきりする。
そもそも、私はもう「味の素」に飽きてしまい、今は料理に大量の「味の素」をかける生活をしてはいない。
なぜなら、「味の素」をかけた食事はどれも均質に”美味く”なることが確定しているため、全く面白くないからである。
先ほどの例えで言うなら、女の顔が全て広瀬すずに見えるようになるメガネを手に入れたようなものだ。
最初こそ醜女が広瀬すずに変じることを喜ぶかも知れないが、どうせどの女も広瀬すずなのだと理解した段階で、もはや満足感はない。
そのくらいなら、各種の料理や食材に固有の複雑な風味に期待したくなるのが人間というものではないだろうか。
狂ったように「CIAOちゅ〜る」を舐め腐るのは猫だけで十分ではなかろうか。